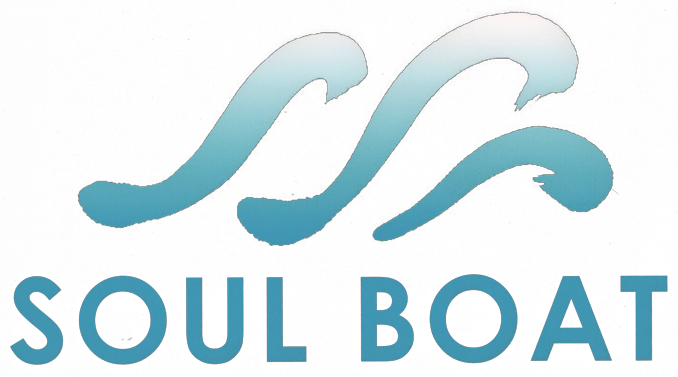ABOUTSOUL BOATについて
- SOUL BOATとは
- 鼎談
<特別鼎談・地域と映画>第6代観光庁長官・田端浩 × 地域力創造アドバイザー・渡邊竜一 × 映画監督・瀬木直貴
渡邊:
本日は日本の観光を政府の立場で牽引して来られた田端さんと映画監督の瀬木さんと私の鼎談ということですが、私は観光と映画業界両方に軸足のある立場です。
各地の観光まちづくりの委員やアドバイザーを務める一方、地域映画のプロデュースやロケ地を活性化する雑誌「ロケーションジャパン」の創刊編集長を務めてきました。
本日のテーマ、地域×映画をこの20年俯瞰的に見て来た経験から発言、進行していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
田端:
よろしくお願いします。
元観光庁長官の田端です。
現在はプー太郎かと思われても嫌だけど(笑)
観光行政について大学で教えたり、アニメツーリズム協会の顧問もやっています。
日本のアニメはポテンシャルが高く、アニメの聖地巡りを目的に海外から多くの旅行者がやって来る、まさにキラーコンテンツとなっています。
しかし、自治体は受け身のところも多い。
私はアニメの聖地を“作る”ことが大切だと思っています。
ハードルは高いけれど。
長官時代も今も「アニメの聖地を作りたい」というような、やる気のある自治体を応援したいという姿勢で、いろいろな活動をしています。
瀬木:
これまで監督・製作した映画全て、地域に根差したオリジナルの物語で、オールロケで撮影してきました。
地域で映画を制作するのは中途半端な覚悟ではできない、一生その地域の皆さんに共感しながら寄り添っていくことが常々必要だと思っています。
日本映画の90%以上は、大手映画会社や放送局が制作されていますが、残りの10%以下がいわゆる独立系、インディペンデントの作品です。
インディペンデントの中でもオールロケでオリジナルの商業作品はごくわずか。
ですので、私は映画業界の端っこの端っこにいる映画監督ということになります。
自虐的ですが(笑)本当のことです。

地域と映画の出会い
渡邊:
映画をはじめ、映像が地方の観光資源となるケースは国内外かなり昔からありますね。
例えば「ローマの休日」のスペイン広場や真実の口、日本では「男はつらいよ」の柴又帝釈天やだんご屋の並ぶ参道などは、映画の方が観光スポットそのものよりイメージとして先に沸きます。
「サウンド・オブ・ミュージック」のザルツブルクや「ニュー・シネマ・パラダイス」のシチリア島などは、映画が観光資源そのものに感じるほどです。
観光行政の観点から、地域と映画との関係をどのようにとらえていますでしょうか?
田端:
地域から見ると映画をはじめとする芸術文化がどの程度の経済効果を持つか、どうしても気になるところです。
しかし、わが国ではこれまで文化が経済に与える影響について確立した指標がありませんでした。
私が長官時代に力を入れたのが、伝統文化や文化遺産、芸術の経済的価値の試算を行うことが出来るようにということでした。
もちろん経済的価値が全てではありませんが、価値の試算を通して伝統文化の保存や職人の育成、観光戦略を立てる場合にも役立つ。
非常に重要なことだと思っています。
また、映画はその土地の魅力を凝縮したものでもあります。
外部の目を通じて地域の人がそれぞれの文化や資源を見つめ直し、魅力を再発見する例が多く見られます。
さらに、外部の人にわかりやすく伝える活動を通じて、地域の情報発信のあり方も変わっていきていることを実感しています。
瀬木:
私の場合は、机上でプランニングしてそれをどこで撮影するかという多くの映画制作と異なり、町に出会い、そこに住んでいる皆さんとの交流があって、その中からその土地ならではのオリジナルな物語が立ち上がってきます。
フィクションから現実へのベクトルではなく、どちらかと言えば、現実からフィクションへのアプローチと言えます。
だいたい半年くらいは空き家やアパートを借りて住み込んで準備をします。
経済的にはとても非効率な方法ですね(笑)
「プロダクトプレイスメント」という言葉があります。
映画の中に企業名や商品が映り込むことにより資金調達や宣伝に綱けるというコマーシャル的な手法ですが、私の作品は「ストーリープレイスメント」ということが出来ます。

映画が地域経済に与える影響
渡邊:
映画と地域の関係を考えるとき、どうしても気になるのは、観光をはじめとする経済への影響です。
日本各地でロケ誘致が盛んになってきていた2000年代初めに、経済効果はどうかということもまちの議会などで話題に上るようになってきていました。
そこで、2007年公開の映画「眉山」という作品を企画時点から追いかけて、経済効果を調べようと四国の経済産業局と調査をしたことがあります。
その際は、撮影による宣伝効果だけではなく、関連した商材、商店街などの集客、入込客の消費額の増加などから、この映画1本で39億円の経済効果が算出されました。
瀬木:
凄いですね!
私は「ご当地映画」という言葉があまり好きではないのですが、観光色が強くなってしまうと観客にはお仕着せになってしまい、結局その土地で見られるだけで広がりがない作品になってしまいます。
映画としてのパワーを失ってしまうと、地域の外の方々がその作品を観て、その土地を訪れるという消費行動に繋がりません。
しかし、かつては「男はつらいよ」近くは「孤独のグルメ」のようなシリーズもの、大河ドラマ「君の名は」「花咲くいろは」といった聖地巡礼現象を起こしたアニメなど、地域の観光に大きく貢献した例もあります。
私が主戦場とする単発のインディペンデント映画では、なかなか観光誘客に貢献できないジレンマを抱えています。
「眉山」は、当然ながら地域の経済効果だけを目的に撮られた映画ではないでしょうが、39億円とは元気が出る数字ですね。
田端:
知る・伝える行動がなければ何も始まりません。
目の前の影響力の大小は関係なく、文化は地域にとって力になると思います。
そこで何らかの気づきがあった時、パブリックがそれを活用し、後押しする姿勢が大切です。
フランスはワインの文化的価値にいち早く気づき、国を挙げて輸出に力を入れ、2021年には過去最高の150億ユーロ(2兆1,000億円)となっています。
かつてフランス映画に名作が生まれ、世界中で観ることが出来ました。
文化の輸出という側面で政府が後押ししています。
日本が何もやっていないわけではなく、国税庁は日本酒の輸出促進のために予算をつけて本気でやっている。
私も周囲に働きかけて、大使公邸で日本酒シンポジウムや商談会を開催するなど少しずつ成果も見えて来ています。
瀬木:
私が監督を務めた「恋のしずく」は、偶然にもフランスワインに対して日本酒の輸出を増やそうとしていた時期に、東広島市に出会ったことで形になった作品です。
酒どころで有名な西条には駅前に現役の酒蔵が7つあり、毎年秋には2日間で25万人以上が集う祭り「酒まつり」が開催されています。
しかし、酒まつりの来場者の属性を聞きますと、9割以上の方々が県内からで、県外や海外から泊りがけで来る人は数パーセントでした。
酒離れ、人口減少時代にあって、交流促進の機会になればと企画し作った映画です。
地元の皆様に応援していただきながら幾つもの試みを行いました。
公開オーディションは、地元で開催するワークショップオーディションで、10人1チームで跳んだり跳ねたりしながら、ゲーム感覚で演技することの楽しさを知っていただく活動です。
1,000名近い方々が来場し、県外からは200名を超えていました。
観光方々来る人もいますが、その中から重要な役に選出することもあります。
映画の中で十分プロと渡り合っている方が、演技未経験の地元の方というようなこともあります。
映画の公開に合わせて、映画の中に登場する日本酒や映画の商標を使った商品を発売しました。
酒蔵めぐりのスタンプラリーも行いました。
製作委員会で把握している数字では、金額ベースで約1億円。
もちろん、そのほとんどは地域に還流するお金です。
さらに、公開月、その翌月と、東広島市西条への観光客数が過去でもっとも観客が増えたというデータがあります。
広島駅や大阪駅、広島空港で映画を活用した観光キャンペーンを行うなど、盛んな情報発信が良い結果につながったのだと思います。
インバウンドと映画
渡邊:
2008年の暮れに、知人の中国人から1本のDVDを渡されました。
中国で大ヒット中の映画だと。
聞くと撮影の舞台が日本の北海道であるらしい。
早速観てみると、50歳前後のさえない風貌の男性がくりなすドタバタ劇。
中国語がわからなかったのですが、近代的なビルが立ち並ぶ中国の風景や、スタイル抜群の美人秘書、インターネットを駆使してやり取りしている様に、驚くほど成長している中国の今が見て取れました。
そして物語の後半のラブストーリーが展開されるところでは、網走や阿寒湖などの素晴らしい風景が映し出されて、印象的なシーンに見とれました。
この映画を見た中国人は間違いなく、北海道に行ってみたいと思うだろうなと確信しました。
それが「非誠勿擾」でした。
早速接点を探して、中国側でアプローチをたくさん試みましたが、なかなかつながらず。
あきらめかけていましたが、出演者の1人で映画の中では男女2人の主人公を北海道で案内する役の、ウーさんとして登場する宇崎逸聰さんが日本にいることを知り、電話番号を調べ、直接アプローチして千葉の習志野に会いに行きました。
そして、北海道の観光関係者やニトリ社の協力のもと、日本国内の配給権と同時に、映画の映像やコンテンツを使っての中国におけるプロモーションをする権利を獲得することが出来ました。
当時の北海道運輸局・北海道庁、そしてJNTOの北京事務所といろいろなPRを行いましたが、北海道のメイン撮影地である釧路市は翌年中国人観光客が14倍に増え、ロケ地となった阿寒湖のホテルは前年比50倍以上になりました。
当時田端さんも観光庁にいらしたので、この作品の影響はご存じかと。
田端:
もちろん知っています!
日本の映画やアニメといったコンテンツを輸出して観光誘客に繋げる活動はもちろん大切ですが、観光からの目線で言えば、何も日本のコンテンツに限らない。
むしろ、外国の映画やドラマの舞台となることの方が訪日客を増やす近道かも知れません。
監督には申し訳ないですが(笑)
瀬木:
いえいえ(笑)
田端:
映画ではありませんが、皆さんもご存じの「瀬戸内国際芸術祭」はインバウンドでも成功を収めている、国もかなりの支援をしてきた現代アートの祭典です。
グローバル化の中で島々の固有性を維持・発展しながら、活力を取り戻そうという試みとして2010年に始まりました。
コロナ禍前の2019年には来場者約118万人、そのうち訪日外国人は約28万人。
経済効果は何と約180億円と発表されています。
最初に申しましたアニメの聖地巡礼も、相当な経済効果をもたらせていると思われます。
瀬木:
私の場合は、監督としては不純な動機かもしれませんが、これからも国際線の飛行機の中で観てもらえるような作品づくりをしたいと思っています。

創作の喜びの中から地域を元気に
瀬木:
私は、これまで全国で50回以上の映画学校にかかわってきました。
そのうち7回は、小学生を対象にした「こども映画学校」でした。
約10名を1チームにして、3日間で数分のショートムービーをするワークショップです。
そこで気づいたのは、まず、子どもたちも自分たちの住む町のことをきちんと考えているということでした。
震災後の福島県浜通りで開催した際には、破壊されたコミュニティを何とか取り戻そうというストーリーが大人の私たちの心を打ちました。
もうひとつは、映画づくりはアクティブラーニングであるということです。
映画学校では、参加者が企画しシナリオを書き、演技をし、撮影するのも参加者です。
参加者の潜在能力が発揮されるのが、目に見えてわかります。
映画に出会ったときの原点を思い出させてくれますし、これからも継続的に開催していきたいと思っています。
渡邊さんもCM塾を各地で開催されましたね?
渡邊:
自分たちのまちに誇りを持てなくなっていると感じる秋田県仙北市の中学校からまちの魅力を映像にしてもらえないかと相談され中学生が絵コンテを描いて、3回の訪問でCM製作までワークショップを重ねて想いを巡らせながら街の魅力を再発見していく様子は子供たちの表情が変わっていくのを体感できましたし、大分県中津市では、廃校の危機にある山間部の分校で美しい風景の耶馬渓とそこで暮らす人々の協力で2つのCMを子供たちが作っていったのですが、そのプロセスを地元メディアがこぞって取り上げてプロセスが話題になり、結果、翌年の入学数が増加し廃校の危機を脱しました。
瀬木 :
ロケ誘致を行う地域側の窓口としてフィルム・コミッションがありますが、その役割も変わってきているように思いますがいかがでしょうか?
渡邊:
そうですね。
2000年に運輸省など複数の省庁が連携してフィルム・コミッション研究会が発足して、大阪を皮切りに全国で相次いで立ち上げられました。
その頃研究会から、今のJFCにつながる流れの中で、ロケ地を横断的に紹介する情報誌の必要性を感じて「ロケーションジャパン」を創刊したのですが、ロケ地観光の流れを加速させたのが韓国ドラマ「冬のソナタ」でした。
2002年に本国で放送され高視聴率を記録。
翌年より、日本でもNHKでBSから地上波と再放送が繰り返され、社会現象になりました。
「冬ソナ」ブームは韓国へのロケ地ツアーが相次いで企画され、物語の舞台となった竜平(ヨンピョン)のスキーリゾートは前年比30倍もの日本人観光客が押し寄せたといいます。
FCが国内で設立され数年たった同時期に、日本でも同じようなロケ地巡りの成果事例が出始めたのを覚えています。
香川県庵治町で撮影された「世界の中心で、愛をさけぶ」などはいい例ですね。
ただ、時を経てネット社会となってフィルム・コミッションよりも映画関係者の方が情報を持っている状況が生まれているので、情報提供としての機能は少なくなりつつある気がします。
映画側が期待しているのは、撮影関連の事務代行と撮影地との交渉をスムーズにする役割です。
一方、フィルム・コミッション側としては、撮影を機に観光に活用したい。
その思惑に、ギャップが出てきているのもあるかと思います。
田端:
海外ではフィルム・コミッションを窓口に、高速道路を貸切ったり、公道でカーチェイスをしたり、かなりの権限を持っています。
わが国ではなかなか困難ですが、文化芸術に対する考えが大きく違っているからかも知れません。
瀬木:
映画の役割はエンターテイメントだけではありません。
多様性を担保することも大切だと思っています。
地域の方から見ると地域で撮ってほしい作品は、ハートウォーミングな感動モノ、爽快なアクションモノなどに限られる傾向にあります。
ゾンビ映画やホラー映画、バイオレンス映画など、地元が望んでいない形での露出になることもあります。
地域のPRという視点だけでなく、映画を芸術として捉える取り組みが問われているのではないでしょうか?

地域への向き合い方
渡邊:
地方創生が謳われ始めたころから、定住人口の減少をどうやって補完していくかが課題となっていました。
それを交流人口による経済効果をと、観光行政に注目が集まることになったと思います。
先ほど話にあったフィルム・コミッションが2000年に発足し、3~4年経過した頃から地域舞台の映画が人気となり、「冬ソナ」の現象もあった流れで、観光庁が2008年に発足となったわけですが、映画やドラマと観光については、観光庁としても意識されていましたか?
田端:
観光交流人口増大による経済効果については、観光庁としても指標を示していまして、定住人口1人当たりの年間消費額を、旅行者の消費に換算して地域の観光行政や観光事業者に理解を図っていました。
定住人口1人の減少分は、国内の日帰り客だと81人、国内の宿泊客だと25人、訪日外国人だとなんと8人招くことで経済的な補完が可能ではないかと。
それに向けて様々な観光施策を進めていく中で、当然映画やドラマについても意識をしていました。
「スクリーンツーリズム促進プロジェクト」その後は「ロケツーリズム連絡会」などと形を変えながら、地域のフィルム・コミッションと連携して観光に撮影を役立てる取り組みを進めていますね。
瀬木:
大手芸能事務所が所属芸人を地域に住まわせる「住みます芸人」という活動を展開していますが、私の場合は「住みます監督」です。
まちと人に惚れ込んで、空き家やアパートを借りて半年以上住み込み、地域の皆さんの暮らしやメンタリティを共有し、共感することから創作を始めます。
というと聞こえはいいですが、いつもうまく進むとは限りません。
ゼロスタートではなく、他の映画会社や放送局が地域に迷惑をかけ、マイナススタートということも多い。
地域の人間関係が映画に反映されることも多いので、そこは注意しなくてはなりません。
地方創生というワードは耳なじみが良く、地方創生を標ぼうする映画人もたくさんいるのですが、現実は地元の皆さんと軋轢が生じたり、レガシーとして何も残さない作品もある。
僕も、若い頃は失敗もしたこともあります。
しかし今では、映画への信頼を無くした地域から「どうすれば映画を作ることができるか?」と相談が寄せられることが度々あります。
地域の皆さんは、映画を通してより良い地域社会を作ることが目的、一方、私たち映画人は、地元の皆さんに喜んでいただき、願わくは世界で観ていただける高品質な作品を作ることです。
目指しているゴールは異なりますが、Win-Winが可能になる方法を模索していきたいと思っています。
田端 浩
愛知県出身。
1981年東大法学部卒、旧運輸省に入省。
2002年国土交通省総合政策局観光部旅行振興課長、2009年観光庁観光地域振興部長、2015年大臣官房長、2016年国土交通審議官、2018年から2020年まで観光庁長官を務めた。
玉川大学観光学部客員教授。アニメツーリズム協会顧問。
渡邊竜一
神奈川県出身。
1991年明治大学文学部卒、広告会社勤務後ベンチャー企業に転身し、リクルートのじゃらんやゼクシイの編集・読者向けイベントの企画制作を経て、2003年ロケーションジャパンの創刊編集長に着任。
以降映画・ドラマの制作過程を活用した地域参加型の観光資源発掘・PRを実践。
現在は主に地域の食・土産品のブランド価値向上や、ツーリズムにつなげる事業を手掛けている。
瀬木直貴
1963年、三重県出身。
立命館大学を卒業後、プロダクション勤務を経てフリーへ。
現在、映像制作会社ソウルボート株式会社代表取締役。
映画監督/TV・CF ディレクター/エッセイ・コラムの執筆/環境・人権に関する講演活動、各地のまちづくりアドバイザーも務め、活躍の場は多岐にわたる。
自然や地域コミュニティーをモチーフにした作品に定評がある。
みえの国観光大使・四日市市観光大使・明和町観光大使・福島県しゃくなげ大使・宇佐市観光交流特別大使。
2008年市制111周年記念・四日市市民文化奨励賞受賞。